ドラマ「夏の香り」と心臓移植の不思議な関係
少し昔の韓国ドラマになりますが、皆さん「夏の香り」という作品をご存じでしょうか?
あの「冬のソナタ」で一世を風靡したヨン様ブームの姉妹編として、2003年に放送されたドラマです。

物語の中心にあるのは、心臓移植を受けた女性の揺れる心。
移植をきっかけに、それまでの自分と、心臓を提供したドナーの感情が入り混じり、戸惑いや葛藤に悩まされる主人公が描かれています。
この「心臓移植で性格が変わる」というテーマは、ドラマだけでなく実際の事例としても語られることがあります。代表的なものに、クレア・シルヴィア女史の『記憶する心臓――ある心臓移植患者の手記』があります。彼女は移植をきっかけに、食の好みや感情に変化を感じ、まるでドナーの心が宿ったかのように思えたと記録しています。
では――心はどこにあるのでしょうか?
脳?心臓?それとも他の場所?
東洋医学では「脳」は主役ではない
西洋医学では「心の働き=脳」と考えるのが一般的ですが、東洋医学は少し違います。
東洋医学では「脳」は「奇恒の腑(きこうのふ)」と呼ばれる特別な器官のひとつに位置づけられています。
奇恒の腑は、臓器とも腑とも違い、飲食の消化や排泄を行うわけでもなく、複雑な機能をもたない特別な存在。脳もその一つであり、「変圧器」のように臓腑からの欲求や情報を統合し、身体に反映させる役割だと考えられてきました。
つまり東洋医学では、心や感情の源は「脳そのもの」よりも、五臓六腑(肝・心・脾・肺・腎/胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)のはたらきにあると見ています。
「腎」と脳の関わり
中医学では「脳・脊髄・骨髄」はすべて「腎」に属すとされます。
腎は成長や発育、生殖をつかさどり、また骨や歯、髪の健康とも深く関係します。
たとえば年齢を重ねると「腎」が弱くなり、白髪や歯の衰えが進み、物忘れが増えていく――こうした現象も「腎の衰え」として説明されてきました。
では「心」とは?
私は「心」とは、最も根本にある臓器の欲求だと考えています。
「お腹が空いたから食べたい」
「疲れたから休みたい」
「愛されたい、認められたい」
こうした欲求があるからこそ、私たちは行動し、複雑な心の世界を形づくっています。
腹が減ればイライラするし、温かいお風呂に入ればほっとする――誰もが経験することですが、これらは臓腑の状態が心に影響している証拠といえるでしょう。
まとめ
東洋医学では、心や感情は脳だけに宿るものではなく、五臓六腑と密接に関わっていると考えられてきました。
だからこそ、体の不調を整えることは、心の安定にもつながります。
当院では、このような東洋医学の考えをもとに、患者さん一人ひとりの体質や状態に合わせた鍼灸治療を行っています。体も心も健やかに保ちたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
七施鍼灸院
大下義武
参考
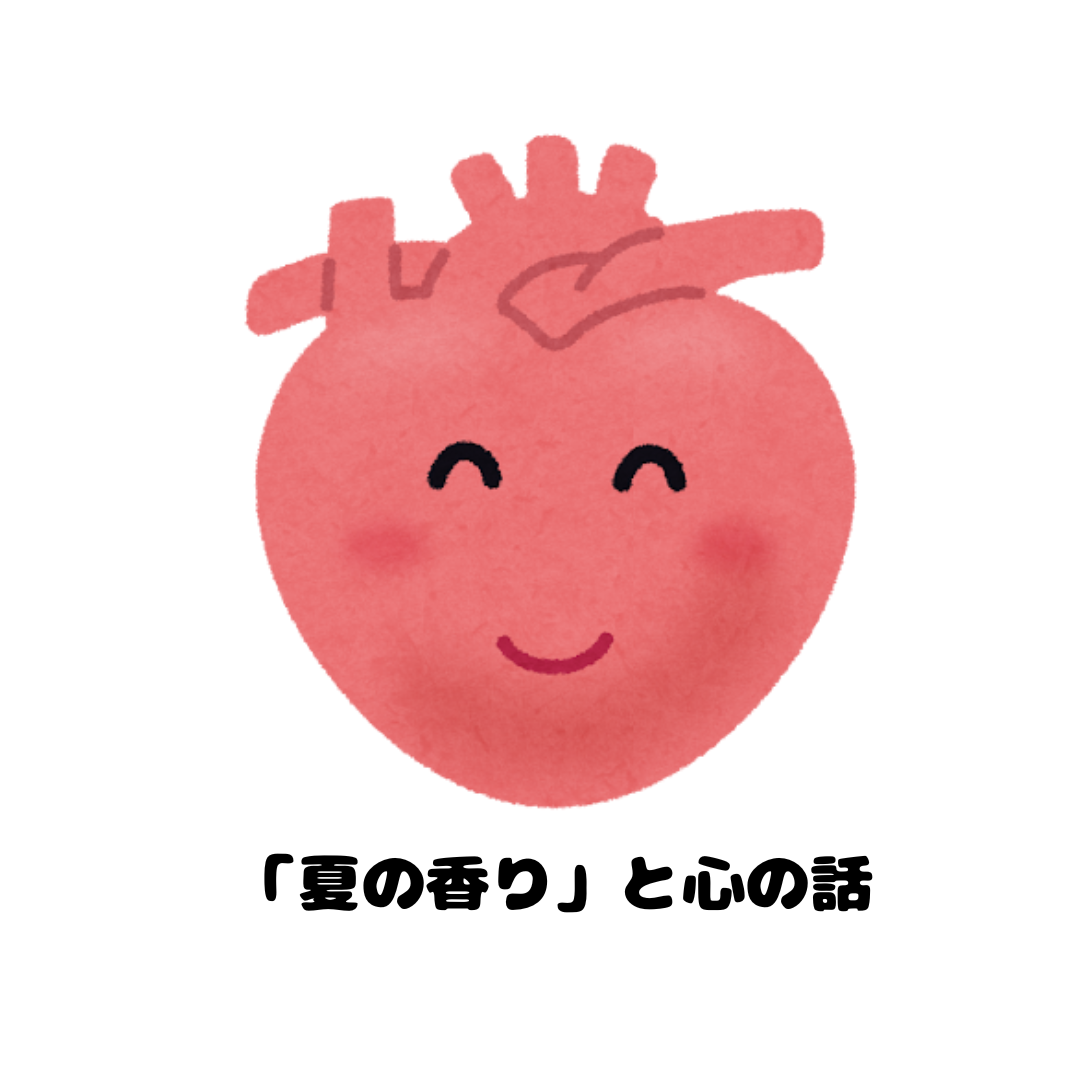
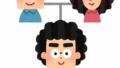
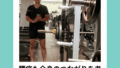
コメント