親子関係と自己肯定感のつながり
母子関係や父子関係が大人になってもうまくいっている親子を見ると、小さい頃の触れ合いがどれほど大切かを実感します。
親子の触れ合いは、その後の親子関係だけでなく、子どもの 自己肯定感 や 共同体感覚 にも大きな影響を与えます。
・・・・・触れるということ、触れられるということ・・・・・
この「触れる」という営みは、人間関係だけでなく、自然界に生きるあらゆる存在にとって欠かせないものです。
教育思想に見る「触れ合い」の価値
感覚を育てる教育を重視した思想家といえば、ドイツの哲学者 ルドルフ・シュタイナー や、イタリア初の女性医師で幼児教育者の マリア・モンテッソーリ が有名です。
賛否はありますが、彼らの教育方針が「触れ合い」の重要性を新しい角度から示したのは事実だと思います。
子どもの「生きる根っこ」は触れ合いで育つ
子どもの成長の根っこは、日々のスキンシップの中で育まれます。
- 抱く
- あやす
- 母乳を与える
- 舐める
これらの「当たり前」を惜しみなく積み重ねることが、子どもの 生きる根 を育てます。
逆に、この根が十分に育たないまま大きくなると、その後いくら学習能力を鍛えても、どこかに無理が生じてしまうように思います。
鍼灸師の視点から見た「触れる力」
鍼灸師という仕事も、鍼を刺す技術だけでは成り立ちません。
いかに安心して治療を受けてもらうか、、
そして鍼灸師は直接「皮膚に触れる」からこそ、安心感を与える触れ方ができなければ患者さんは心を開いてくれません。
もちろん、雰囲気だけで治療を行うカリスマ的な先生もいますが、「触れながら問診し、触れながら治療する」ことこそ鍼灸師の大きな強みだと私は思います。
子育てと鍼灸に共通する「皮膚感覚」
鍼灸師として「皮膚感覚を大切にせざるを得ない」仕事を続けてきたことで、子育てにも応用できたと感じています。
実際、皮膚感覚を豊かに刺激されて育った子どもは、ある時期に加速度的に成長します。
こどもたちをみて、それを無茶苦茶実感しています。
動物としての根っこを育む
結局のところ大切なのは、子どもの「動物としての根っこ」をどう育むか。
この根っこさえ備われば、子どもは自分の力で学び始めますし、その根っこさえ育てば、遠くに羽ばたいていけると思うのです。


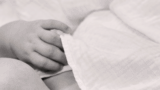
コメント