『センス・オブ・ワンダー』(レイチェル・カーソン 著)をご存知ですか?
私の手元にあるのは少し古い「佑学社」版
久しぶりに読み返してみて、あらためて――やっぱり、いい本だなぁ…としみじみ思ってしまいます
レイチェル・カーソンは、アメリカの海洋生物学者
代表作『沈黙の春』で農薬や殺虫剤による環境汚染の実態をいち早く告発しました
これが当時のケネディ大統領にも大きな影響を与え、DDTという農薬の全面禁止にまでつながったことは、環境保護の歴史における象徴的な出来事です
「知ることは、感じることの半分も重要ではない」
学習能力がもてはやされる今の時代、
この言葉にピンとこない方もいるかもしれません
でも、レイチェル・カーソンは『センス・オブ・ワンダー』の中で、
知識よりも“感性”を育てることの大切さを、繰り返し説いています
「知る」ことよりも、「感じる」こと
子どもが何かに心を動かされたときに初めて、
“もっと知りたい”という意欲が自然と生まれてくる
そうして得た知識こそが、真に身につくものだと
私も、まさにその通りだと思います
生きやすさ
それは、知識の量より、心が動く経験の多さに宿るのかもしれません
そしてカーソンは、その“感性”を育む最良の場として、
**「自然」**をあげています
森の中で風に触れ、雨のにおいを感じること
小さな虫や、きらきら光る水面をじっと見つめること
そんな時間こそが、豊かな心の土壌を耕してくれるのだと
あと、私が感じたもう一つの印象的な言葉、、
「子どもには、一緒に驚いてくれる大人が少なくとも一人、必要です」
たとえ自然に囲まれていても、
その美しさや不思議さに気づけない大人が、増えているように感じます
風のにおい、草の揺れ、虫の声
そんな自然のささやきに耳をすまし、
子どもと一緒に驚き、面白がってくれる大人の存在、、
それこそが、子どもの感性を伸ばすための豊かな土壌になるのだと思います
本を読みながら、あれこれ考えることしきりです
子どもの目線でもう一度自然を見つめてみる
それは、私たち大人にとっても「感じる力」を取り戻す大切なことにつながるかもしれません
……以下本文より……
わたしは、子どもにとっても、どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。
子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。
美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。
消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。

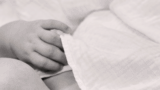
コメント