
> 前にYahoo!ニュースで「教育と格差」に関する記事を読みました。そこではSES(社会経済的地位)と学力の関係について議論されていましたが、私が強く感じたのは「知能には遺伝の影響がある一方で、教育にも力がある」ということ。
人には、生まれながらに持っている知能のベースがあると思います。
教育や努力で伸ばせる部分はたしかにありますが、それでもどうしても遺伝的な要素が大きいことは否めません。
認めたくはありませんが、背の高い親から背の高い子が生まれやすいように、知能にも親からの影響は強く刻まれているのだと思います。
もちろん教育には「力」があります。
ただ、「教育さえあれば遺伝的な差を埋められる」と言い切るのは如何ともしがたい問題です。
本物の秀才に出会うと、その差は単なる努力だけでは越えられないのだと感じることがありますから。
高学歴の親のもとで育った子どもが自然と勉強を続ける習慣を身につけるのも、環境と遺伝が重なっているからこそ。
家の中に「知的に楽しんで学び続ける大人」がいることは、何よりの教育なのかもしれません。
それでも「うちの子には才能がない」と諦めるのは違うと思います。
子どもたちの中にも、高校までは学力が思うように伸びませんでしたが、自衛隊に就職し、じっくり時間をかけて力をつけて、幹部候補生学校を卒業して今に至る子もいます。
そんな風に、ゆっくり育つ子もいる。
親は、その子の歩みの速さに寄り添うことが大切なのだと、子育てが終わった今、つくづく思うのです。
とにかく、短い時間でスッと理解できる子もいれば、時間をかけて学ぶ子もいます。
「その子のペースで学んでいける工夫」を周りがしてあげれば、どの子も確実に力をつけていけるのだと思うのです。
結局、社会が本当に求めているのは「人としての総合力」。
浪人しても、留年しても、社会人になってから大学に行っても構わない。
いや、大学ありき、というのもこの時代に合っているのかと思っている節すら私にはあります。
そんな、いまだに世間にはびこる一律に18歳で大学に進学しなければならない、という思い込みこそが、子どもを苦しめているのではないでしょうか。
子どもを急かしちゃだめ。
「今のままでいい」「いや、今のままがいいんだよ」と言ってあげられることが、どれほど子どもを安心させるか。
心に苦しみを抱える子どもや、自ら命を絶ってしまう子が増えている今だからこそ、
「みんなと同じでなければいけない」という幻想を手放すことが、子どもの心を守る第一歩になるのかもしれません。
子どもは、それぞれの速さで育つ。
親がしてあげられる一番のことは、「そのままでいい」とそっと寄り添うことだと思います。
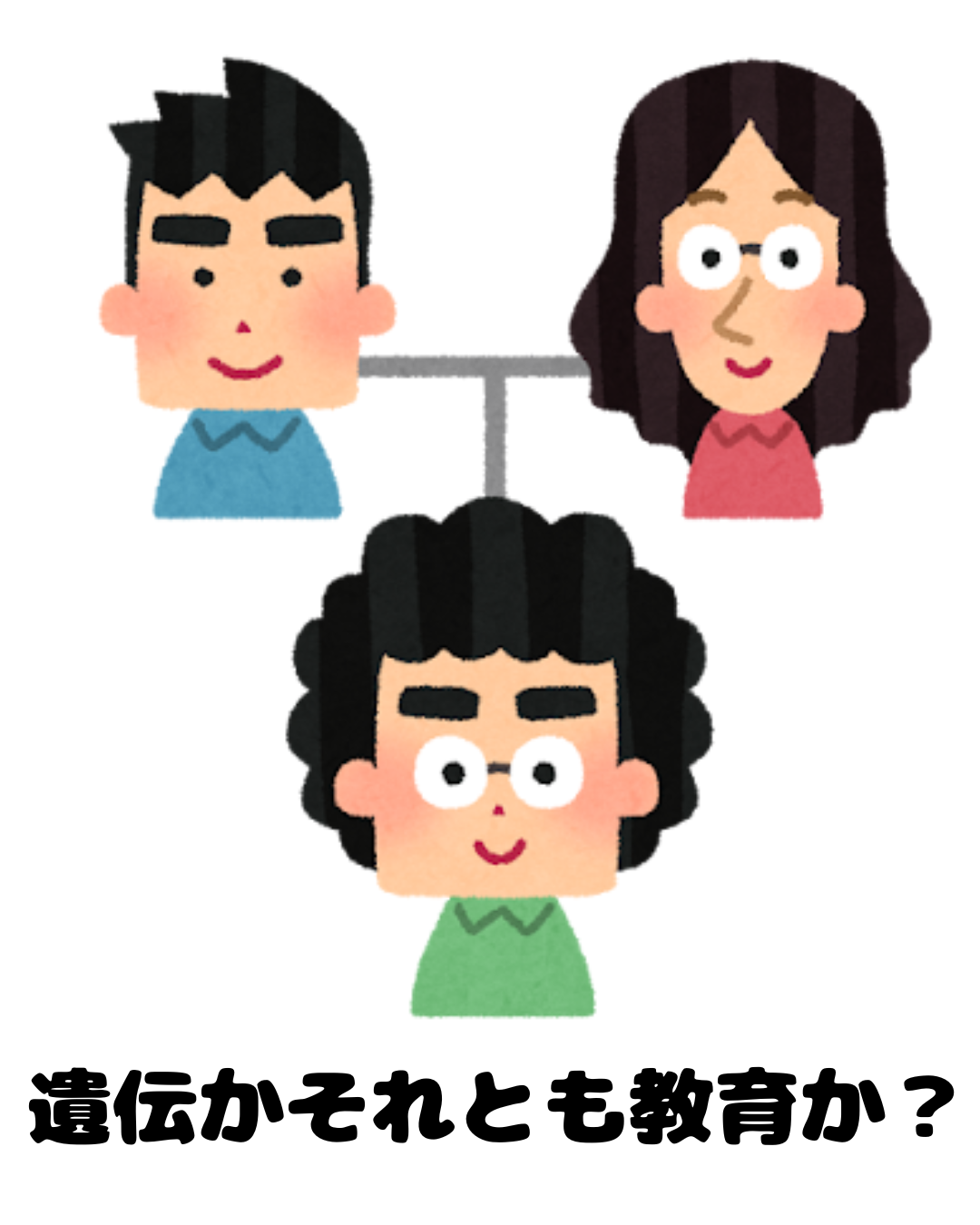




コメント