みなさんは「陰陽五行(いんようごぎょう)」という言葉を聞いたことはありますか?
私たち鍼灸師が治療方針を決める際にとても大切にしている理論です。
少し難しそうに感じるかもしれませんが、実は自然の流れを観察して生まれた、とてもシンプルな考え方なんです。
陰と陽 ― すべてを二つに分けてみる
昔の人は、宇宙の始まりを「太極」と呼び、そこから陰と陽に分かれたと考えました。
自然界を見てみると…
- 昼と夜
- 天と地
- 上と下
- 夏と冬
- 火と水
このように、すべてのものを「陰」と「陽」に分けることができます。
ただし、陰と陽はどちらか一方だけで存在するのではなく、常に変化しながらバランスを取り合っているのです。
五行 ― 木・火・土・金・水のつながり
さらに自然を観察すると、ものごとは「木・火・土・金・水」の5つの性質に分けられると考えられました。
助け合う関係(相生)
- 木が燃えて火を生む
- 火が燃え尽きて土になる
- 土から金が生まれる
- 金から水がしたたり落ちる
- 水が木を育てる
抑え合う関係(相剋)
- 木は土の栄養を吸う
- 土は水をせき止める
- 水は火を消す
- 火は金を溶かす
- 金は木を切る
こうして、自然はお互いに支え合ったり抑え合ったりしながら循環していると考えられました。
人の体と陰陽五行
古代の人は「人の体も自然の一部」と考え、五行を臓器に当てはめました。
- 肝 → 木
- 心 → 火
- 脾 → 土
- 肺 → 金
- 腎 → 水
たとえば「肝(木)の働きが乱れると、心(火)や脾(土)にも影響が出る」と考え、全体のつながりを大切にしました。
病気と健康の見方
東洋医学では…
- 健康:自然との調和がとれている状態
- 病気:調和が崩れた状態
と考えます。
たとえば「腎の陰」が不足すると、火の性質が強くなり、手足のほてり・口の渇き・不眠・便秘などが起こる、と説明されます。
体の不調は「一つの臓器の問題」というよりも、全体のバランスの乱れととらえるのが特徴です。
まとめ
陰陽五行は、占いのような不思議なものではなく、自然の観察から生まれた考え方です。
そのシンプルな理論は、鍼灸や東洋医学の治療の基本となっています。
当院では、この陰陽五行の考えをもとに、患者さん一人ひとりの体質や症状に合わせた治療を行っています。
自然と調和した体づくりを一緒に目指していきましょう。
広島県安芸郡
七施鍼灸院
大下義武

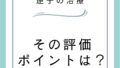
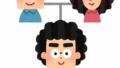
コメント