示談までに10年かかった交通事故や、出産時に肺が未成熟でNICUに入った出来事、、
さまざまな経験を経て、私の子育てに対する考え方は形作られてきたのだと思います
正直に言えば、最初の頃はかなり無責任に子育てをしていました
その証拠に、車や人通りの多い道で、まだ2歳だった子の手を繋がずに歩いてしまったこともあったのですから
結果として事故に遭わせてしまい、包帯に巻かれてベッドに横たわる子どもの寝顔を見ながら、
「この子がいなくなったらどうしよう」
と初めて強烈な不安に襲われました
その時の恐怖は、今でも鮮明に覚えています
そのような体験を通して、私は少しずつ子育てに真剣に向き合うようになりました
もし何事もなく過ごしていたなら、今の自分はいなかったかもしれませんし、子どもへの考え方もまったく違うものになっていたと思います
もちろん二度と経験したくない出来事ですが、あの試練が家族をひとつにまとめてくれたのは確かです。¥
だから、私の子どもへの思いは今もひとつ
「生きててくれてありがとう」
いろんな方の子育てに触れる中で感じるのは、子どもが自分なりの「生きやすい場所」を見つけているご家庭ほど、親が子どもを思い切り甘やかしているということです
「甘やかす」という言葉は、子育てではネガティブに受け取られることもあるので使いにくいのですが、実際に素敵に育っている子どもたちを見ていると、どの家庭も子どもの「好き」や「やりたい」をとても大切にしているように思います
だから私は、子どもを遠慮なく甘やかしてほしいと願っています
子どもは、親にしっかり甘えることを許されて初めて、こう感じられるのだと思います
「私はどこへ行っても、誰からも愛される存在なんだ」
この“根拠のない自己肯定感”があるからこそ、子どもは安心して遠くへ羽ばたいていけるのではないでしょうか?
でもある時この話を中学校の先生をしている患者さんにしたら、
「だから子離れできない子が増えているんですよ!」
と一蹴されてしまいました(^◇^;)
それでも私は、やはりこう思います
「自分は一人じゃない」と心から感じられることこそが大切なのではないかと、、
それこそが、子どもが社会で生きていく大きな力になるのではないでしょうか
「お母さん、手を繋いで!」
子どもがそう求めてきたとき、何をさておいても応えて手を繋ぎ、触れ続ける
私はそれこそが、将来その子が社会で生きていくための大切な基盤になると思っています
山極寿一先生は
「ゴリラの群れは接触を通じたつながりで維持される」
と語っておられますが、この言葉は人間にも確実に当てはまります
でも最近は、小さな子どもにタブレットを与え、視覚に偏った生活をさせすぎている方が多いように思っています
触覚・味覚・嗅覚など、体に近い感覚が育つ前に視覚に依存してしまうと、子どもの自己形成にさまざまなマイナスの影響が出てしまう、、
最終的には脳でつながる社会で生きていくとしても、、
幼い時期には「触れ合う」ことを一番に大切にしてほしい
私はそう強く願っています
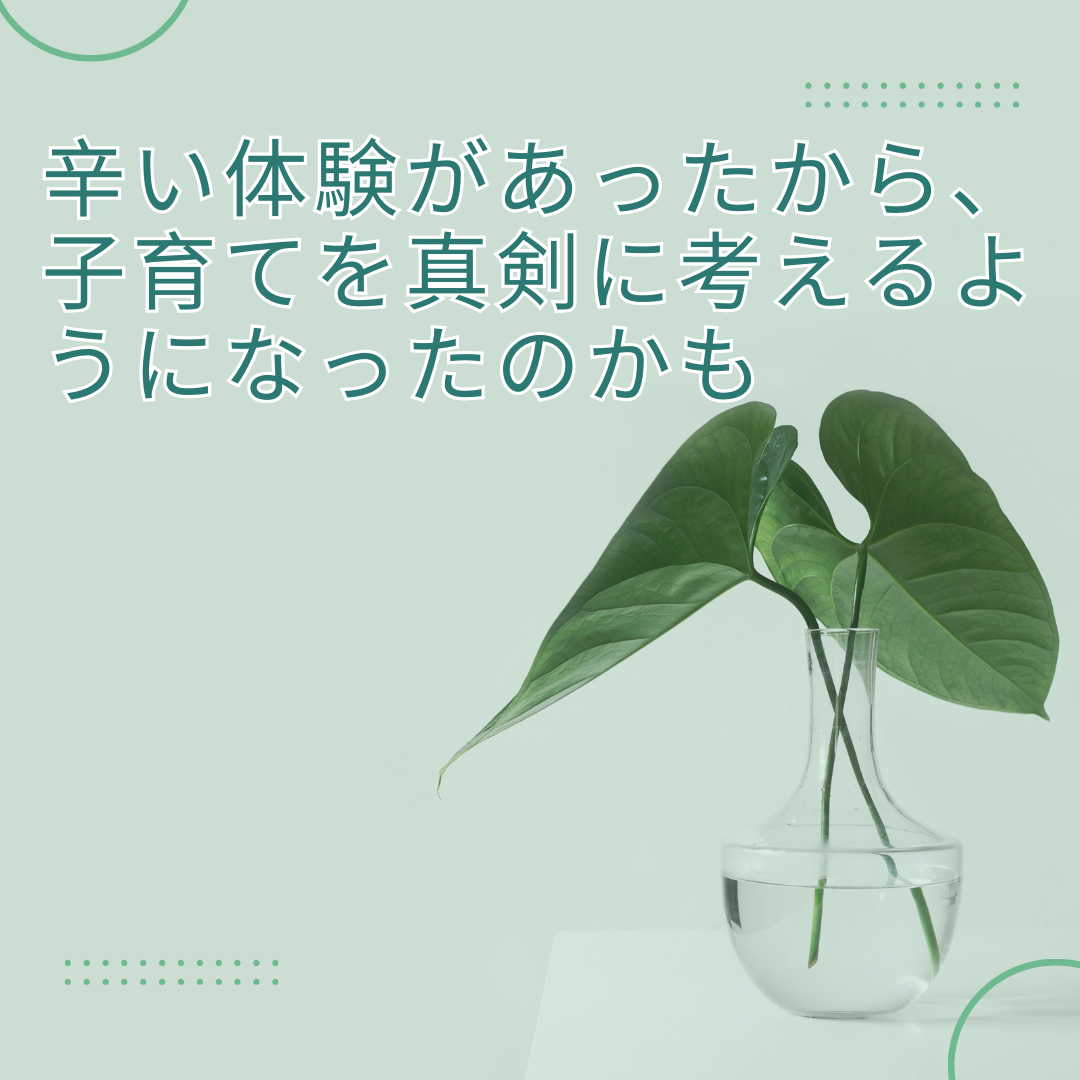
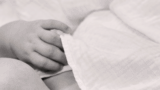
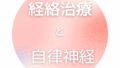
コメント