五木寛之は著書『こころ・と・からだ』の中で、
「人は政治も教育も簡単には信じないのに、医師や病院の言うことはあっさりと信じてしまうのはなぜだろう?」
といった趣旨の問いを投げかけています(原文そのままではありません)。
確かに、私たちは「医療」に対して、どこか特別な信頼を寄せています。
それが命に関わることであるほど、
「先生が言うなら」
「病院でそう言われたから」
と、自分の感じ方や希望よりも「医療の正解」に従おうとしてしまう。
本来なら、
その人が「どう生きたいのか」「どう死にたいのか」を丁寧に話し合い、
そのうえで最善の医療を選ぶべきではないでしょうか。
しかし現実は、
チューブにつながれ、身動きの取れないまま生かされ、
食べる喜びさえ失っても「ありがたい」と思おうとする。
いや、そこまで酷い状態でなくても、
ウイルス感染に抗生剤を出され、せっせと飲み続けていたり、
胃の粘膜に負担をかけるような薬を、長いあいだ飲み続けていても、
「先生が言うなら間違いない」と自分に言い聞かせてしまう――。
そんな人生の先輩方の姿に触れるたび、
私は「生きる」と「生かされる」の違いについて考えさせられるのです。
私たちはいつの間にか、
病院が提供する「延命」という名の治療を、
“ありがたく受け入れるもの”として刷り込まれてしまったのかもしれません。
本当の意味での「医療」とは、
病気を治すことだけではなく、
その人の「生き方」や「死に方」も含めた
包括的な視点から寄り添うことだと思います。
鍼灸の世界には、「からだ」と「こころ」はひとつ、という考えがあります。
どんなに小さな痛みでも、それは生き方の一部とつながっています。
だから私は、「からだを診る」ことを通して、
「その人の生き方」にも耳を傾けていきたい――
そう、心から思うのです。
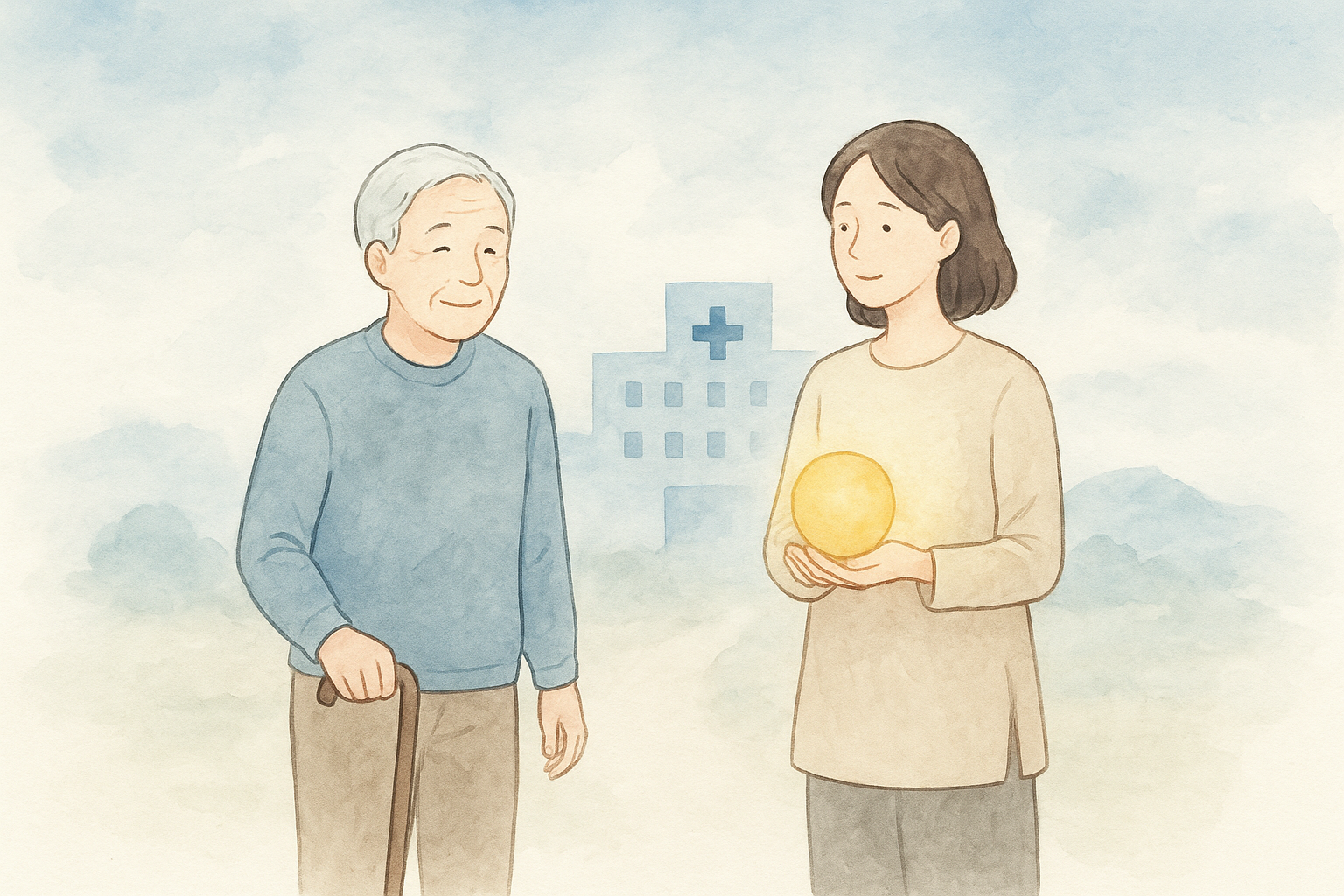
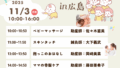

コメント