喉に刺さった魚の骨を取ってほしいという目的で鍼灸を受療された方の話
10日ほど前に喉にサバの骨が刺さり、それがどうしても取れないという方が来院されました。
MRIを撮っても特に所見はありませんでしたが、炎症の痕は残っていたため、「痛みがあったことは嘘ではない」と医師にも理解はされています。
ただ、実際に骨は映っていないので、表向きは親身にしてくれていても、内心では信じてもらえていないことを、ご本人も感じていると言っていました。
どうにもこうにも喉に骨が刺さっているような感覚が辛く、色々と調べていくうちに、YouTubeで「喉に刺さった骨を取るには内関というツボが良い」という動画を見つけたそうです。
そして近所の鍼灸院に片っ端から電話したものの、どこも「そんな迷信を信じるな」「うちでは無理だ」と、けんもほろろの対応だったとか。
その流れでうちにも電話をかけてこられたのですが、私の対応が「なんだか面白がってくれている」と感じてくださり、来院につながりました。
東洋医学的考察の面白さ
もちろん、まずは「本当に骨が刺さっているのか?」という疑いを含め、西洋医学的な観点も踏まえて施術に臨むのは当然のことです。
しかし、それ以上に東洋医学的にこの症状をどう捉え、どう治療方針を組み立てていくかという作業は、私にとって、嬉しくありがたい作業でもあります。
今回は、症状が顎下の「大迎」というツボあたりにあったので、胃経か大腸経の反応を診てみました。
すると同側の合谷に強い反応がみられました。
YouTubeで紹介されていた内関は、反応がよくわかりませんでしたが、念のためお灸をして脈の変化を確認しました。
証としては、肝虚で胃に旺気実があるとみえたので、その治療を行いながら脈を穏やかにし、加えて異常に硬くなっていた肩甲挙筋を緩めました。
治療方針と鍼灸師の醍醐味
本当は、内関というツボだけを使って「そこがどう効くのか」を試してみたかったのですが、反応があまりにわかりにくく、このツボだけで帰っていただいて「何の効果もなかった」と思われるのはやはり避けたいと感じ、本治法に加えて合谷、さらに肩甲挙筋へのアプローチを行い、主訴がどう変化するかをみることにしました。
治療方針をあれこれ考えるのは、鍼灸師にとって本来とても面白く、やりがいのある作業だと思います。
ましてや「喉に刺さった魚の骨を取ってほしい」という依頼を鍼灸師に託してくださるなんて、正直ワクワクせずにはいられません。
しかし残念ながら、最近はこうした面白さを手放してしまう鍼灸師も多いようです。
せっかく東洋医学を学んできたのになぜだろう……と、少し不思議に感じます。
もちろん、東洋医学的な考察がうまくはまらず、結果として来院されなくなる方もいます。
でも逆に、劇的に良くなる方もいるのです。
その経験をまた次の治療に活かし、治療を組み立て直せることこそが、この仕事の醍醐味。
それなのに、今はどうしても教科書通りのことしかしたがらない人が増えているのは、時代の流れなのでしょうか。
だからこそ、こうした症例には内心ワクワクしながら向き合っていますし、経絡治療を学べたのは本当に幸運だったと感じています。
治療というフィクション
治療そのものは「現実」です。
でも治療方針は、鍼灸師の数だけ――いや、医師も含め、その患者さんの治療に携わる人の数だけ存在します。
登り方はそれぞれ違っても、「治す」という頂きを目指す思いは、きっと同じなのでしょう。
なぜなら鍼灸師は、自らの五感を総動員して、患者さん一人ひとりの“治療の物語”を構築していくからです。
東洋医学の診断法である四診から得た情報をもとに、身体の状態を読み解き、一つの物語を紡ぎ出していく作業。
論拠が確かであればこそ、その物語は治癒への道しるべとなるはずです。
こうしたストーリーを描き続ける力こそが、私たち治療家にとって最も大切なのだと感じています。
「日本鍼灸へのまなざし」 松田博公 著
出版者・出版年月 ヒューマンワールド・2010年6月~~~~ 抜粋 ~~~~
井上鍼灸学の核心をフィクションという概念に凝縮できるのではないかと、私は考えている。先生の言うフィクションとは、嘘や虚構ではない。事実や仮説を含む物語でありながら、それを適用すれば思い通りの治療結果が出る構造的な思考とでも呼ぶべきものである。脈状診も六部定位診も、経脈・経穴・五臓六腑もすべてフィクションであり、証もまたフィクションなのである。つまり、それらはなんら事実ではない。
四診によって得られる情報は、鍼灸師の五感を通して統合され、優先順位が決められます。
現代は、自然から離れ、薬に頼る生活を送る人も多く、望診では「肝」のサインが強いのに、聞診では「腎」、問診では「肺経」に異常が見え、切診では「脾虚」しか感じられない──そんな患者さんも少なくありません。
だからこそ、今の時代においては、鍼灸師自身が組み立てる“治療の物語”がいっそう重要になるのです。


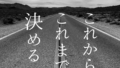
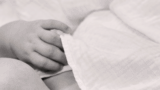
コメント