心は脳にではなく内臓にある ☜消去する
「心」はどこにあるのでしょう?東洋医学と内臓の記憶
東洋医学の文献等を読んで、ふと思うがあります
それは「脳」についての記述が、驚くほど少ないということです
脳という臓器の存在を知らなかったのか、それとも全く重要視していなかったのか、、
その理由は定かではありませんが、少なくとも今日のように、脳を「心や意識の中枢」として語ることは、東洋医学にはあまり見られません
現代では、「心はどこにあるのか?」と尋ねると、多くの人が「脳だよ」と答えると思います
でも口腔外科医・西原克成先生の著書『内臓が生みだす心』を読んだとき、私は東洋医学が「心」を内臓に求めていた理由に、進化論的なところからの裏付けがあるのではないのかな、って思ってしまいました

内臓に宿る「心」
西原先生は著書の中でこう述べています。
腸管内臓に宿る心の源になる財・名・色・食・睡・の五欲は、三つの欲に収斂します。先ず一つ目が食欲で、これが財欲・所有欲の源です。次が色欲で、名誉欲につながる性欲で征服欲でもあります。睡は、身体の体壁系内臓系をあわせたリモデリングの欲でスポーツのあとの回復期の筋肉感覚にも通じる欲です。
つまり、循環器や泌尿・生殖器なども含めた内臓の欲求が複雑に絡み合い、私たちの欲望や行動パターンを形成しているといことなんじゃないかな、って、、
とすれば、精神活動や性格も内臓の状態やバランスによって変化しうるということになると思います
一本の管から生まれた命
西原先生は、「脊椎動物を含め生物はもともと一本の管から発達しました」と言っています
そして、
…三十数億年に及ぶ記憶が私たちの内臓にしみこんでいる。その内臓のリズムは宇宙のリズムにつながっている。…
とも述べています。
この感覚は、東洋医学で語られる「気」の概念と重なるように思います
「気」は、気持ちの“気”であり、経絡現象を生み出すエネルギーでもあります
鍼灸によって経絡の流れが整えば、気分や感情に変化が起こり、それが内臓の状態にまで影響を及ぼす、、
こうした一連の体験は、私たち臨床家が日々の現場で感じていることでもありますよね
なぜ東洋医学は「脳」を重視しなかったのか?
東洋医学が脳を重視しなかった背景に思うことですが
心や意識の中枢は「内臓のリズムやその全体性の中にあるもの」と捉えていたという認識があったからなのではないでしょうか?
そう考えるようになったのは、鍼灸を通じて内臓の調整が感情や精神状態に影響を与えるという経験を、繰り返し実感してきたからです
脳は確かに高度な情報処理を行う器官です
しかし、命の深層には、もっと原始的で根源的な“リズム”であり、私たちの内臓に刻まれたその記憶こそが、心のゆらぎや感情の基盤を形づくっているように思うのです
参考
- 西原克成『内臓が生みだす心』
- 布施英利「三十数億年の生命の記憶」『考える人』2003年春号

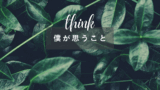
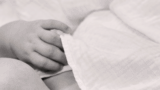
コメント