東洋医学の四診と五感
検査機器のなかった時代、東洋医学では「四診(ししん)」と呼ばれる独自の診察法によって、患者さんの状態を見極めてきました。
この四診ですが、「望診・聞診・問診・切診」の四つから構成されます。
- 【望診】
顔色や表情、肌、爪、そして舌を観察する「舌診」など、視覚を用いた診察です。患者さんの外見から内側の状態を読み取ります。 - 【聞診】
声の大きさや高さ、発音の仕方、さらには体から発する匂いなど、聴覚と嗅覚を駆使して行う診察です。 - 【問診】
病歴や生活習慣だけでなく、体質やちょっとした一言も大切な情報として五行に当てはめ、治療方針に生かします。 - 【切診】
脈や腹部をはじめ、手足や背中などに直接触れて行う、触覚による診察です。脈診・腹診が中心となります。
この流れからもわかるように、東洋医学では、いきなり体に触れることはありません。むしろ、名人ともなると、患者さんから症状を聞く前に、五感を研ぎ澄ませて観察を始めるのです。
何気ない会話の中で声の調子を感じ取り、ふとした仕草や匂いを捉える。そしてある程度の推察を経た後に、ようやく問診、最後に切診へと進むのが基本の順序です。
たとえば、経絡治療のモデルとなった鍼灸の大家・八木下勝之助翁ですが、彼は『鍼灸重宝記』のみを教科書とし、虚している一つの経絡にだけ補法を施すという極めて非常にシンプルで的確な治療を行っていました。感覚があまりに鋭敏だったため、「通りを歩く足音だけでその人の死期を見抜いた」といった伝説が残っています。
このように、四診を駆使して行われる経絡治療ですが、長年この道を歩んできた鍼灸師たちが集う勉強会でも、同じ患者さんに対して「脾虚」「肝虚」「腎虚」と、診立てが分かれることはよくあります。
こうした“ばらつき”をもって、「東洋医学は曖昧だ」と信頼を失い、経絡治療の道を離れる鍼灸師も少なくありません。しかし、それは西洋医学的な「エビデンス至上主義」の視点から見た場合の話です。
四診で診立てに違いが出るのは、ある意味当然のこと。
なぜなら、鍼灸師は自らの五感を総動員して、患者さん一人ひとりの”治療の物語”を構築していくからです。
同じ患者を診ても、受け取る感覚はそれぞれ違います。それゆえ、勉強会などで「そのストーリーで治療を進めていくのですね」と認め合う場面に、東洋医学ならではの趣(おもむき)を感じるものです。
四診によって得られる情報は、鍼灸師の五感を通して統合され、優先順位が決められます。
現代は、自然から離れ、薬に頼る生活を送る人も多く、望診では「肝」のサインが強いのに、聞診では「腎」、問診では「肺経」に異常が見え、切診では「脾虚」しか感じられない──そんな患者さんも少なくありません。
だからこそ、今の時代においては、鍼灸師自身が組み立てる“治療の物語”がいっそう重要になるのです。
そう、患者三様、十人十色。
四診で得られた情報に、自らの五感を重ね、目の前の一人に向き合いながら、治癒へと導く“壮大な物語”を紡いでいくのです。

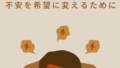

コメント