加藤諦三先生の著書にこんな言葉があります
過干渉も放任も親の無関心
「放任」と「無関心」は結びつくのですが、
「過干渉」と「無関心」が同じ意味合いを持つという点に少し戸惑ったのを覚えています
なので、はじめてこの言葉を聞く時、そう思われる方もおられるかもしれません
この言葉ですが、
過干渉の親は、たいてい自分自身の不安や欲求を子どもに投影します
なので子どもに関心があるようでいて実は自分にしか関心がないという感じでしょうか?
その結果子どもは親の思い通りに動く道具のような存在になってしまう、、
そしてもし子どもが親が敷いたレールから外れようとすると、親はたちまち不機嫌になる、、
子どもはその空気を敏感に察して、
親の顔色をうかがいながら従うしかなくなるのです
不機嫌という無言の圧力で子どもを支配する
これが、加藤先生の言う「過干渉=無関心」という構造なのだと思います
ところで
「子は親の鏡である」とよく言います
実際子どもを見ればその親の在り方が見えてくるものです
もちろん、すべてがそうとは言えませんが、子どもの姿には、親の価値観や接し方が、どこかににじみ出ているのは本当のところ、、
なので親がどんなに社会的地位があろうが素敵な言葉を持っていようが
その方の子どもの姿は結構その方を量る上で参考にしています

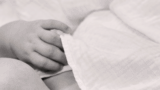
コメント