既存の宗教への反発から新しい宗教は生まれる
仏教はカースト制度への反発から、キリスト教はユダヤ教の「選ばれし民」という思想への否定から生まれたと聞いたことがあります。多くの宗教は、それぞれの時代に支配的だった価値観や宗教に対する反発を原動力に、広がっていったという歴史があるようです。
これまで私は、ユダヤ人といえば「ホロコーストを経験し、長く国を持たなかった、虐げられた民族」という印象を持っていました。けれど「キリスト教はユダヤ教の選民思想に対するアンチテーゼとして誕生した」と書かれた本を読み、さらに現在のイスラエルが敵対勢力に対して「殲滅も辞さない」といった強硬な姿勢を見せている様相を知るにつれ、その見方は大きく揺らぎました。
ユダヤ人自身、「選ばれた民」という優越意識を持っていた歴史がある。そう考えると、「人を救う」ことを掲げる宗教ですら、差別や対立と無縁ではなかったのかもしれません。皮肉なことに、宗教は差別という構造の中でこそ生まれ、力を持ってきたとも言えるのではないでしょうか。
そしてこれは宗教に限った話ではなく、差別する側とされる側は、時代によって簡単に立場が入れ替わるものなのだと、あらためて思います。人間の歴史には、怒りや妬みといった感情が深く関わっているのだと感じずにはいられません。
そんなことを考えていたら、ふと学生時代のことを思い出しました。京都・出町柳駅の近くに住んでいた頃の話です。この地域はかつて被差別部落とされていた場所、市営住宅や、100円で入れる公共の風呂があって、学生にとってはありがたい場所でした。でも、その整備の背景には、かつて差別されてきた人々が行政に働きかけ、優先的に入居できるようになった経緯があるそうです。そこにも人の歴史が感情によって動かされてきた一端が表れているように思いました。
歴史をたどればたどるほど、「宗教があっても差別はなくならない」という現実が浮かび上がってきます。
宗教ではありませんが、ヒトラーもまた、分断されていたドイツをひとつにまとめるために、ユダヤ人という“共通の敵”を作り出し、それを巧みに利用しました。そしてヒムラーやゲッベルスといった側近たちが「ヒトラーに気に入られたい」という思いから暴走し、悲劇を加速させていったのです。
宗教や思想の世界では、カリスマ的な教祖が現れると、その人に取り入ろうとする周囲の人々が、過激な行動に出ることがあります。かつてのオウム真理教の事件もそうですし、人民寺院の集団自決事件も、教団が引き返せなくなった背景には、教祖本人だけでなく、周囲の暴走があったのではないかと思います。
そう思うと、今では穏やかな印象を持たれている創価学会も、教祖の存在感が非常に強かった時代には、今とは違った面を持っていたとしても不思議ではありません。
「個人の信念」が「集団の正義」へとすり替わったとき、人は時としてとても危うい選択をしてしまうものです。だからこそ、どんな思想や信仰であっても、東洋思想に学ぶような「中庸」の心を持ち続けることが、現代に生きる私たちにとっても大切なのだと、つくづく思います。


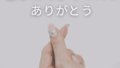
コメント