経絡治療と「皮膚」の不思議な関係
私が行っている鍼やお灸を用いた経絡治療は、基本的に体表への刺激を中心としています
もちろん、血液循環の改善や鎮痛を目的とした深めの鍼を行うこともありますが、治療の主眼はあくまで「気」の調整にあります
そのため、皮膚に軽く触れるだけの浅い鍼がメインです
「気」の働きを意識することで、驚くほど大きな効果を得られるのが経絡治療の特徴です
経験と科学をつなぐ視点
経絡治療の理論は、長年の臨床経験に基づいて築かれてきました
ですから多くの場合は実際に効果を体験することで理解されるものです
でも一方で、現代医学的な視点からも少しでも納得感を持っていただければと思い、今日はそのあたりをお話ししてみたいと思います
「皮膚」が持つ大きな役割
私自身、東京スキンタッチ会で桜美林大学の山口創先生のお話を伺ったり、『皮膚は考える』の著者・傅田光洋先生の本を読むことで、「なぜ鍼をツボに当てるだけで治療が成立するのか」を別の角度から理解できるようになりました
そこで改めて見えてきたキーワードが 「皮膚」、なかでも「表皮細胞」 です
経絡治療の奥深さは、まさにこの「皮膚」と深く関わっているのかもしれません
表皮細胞と視床下部の関係
皮膚は外側から「角層・表皮・真皮・脂肪組織」という層構造になっています
この中で鍼灸治療と特に関わりが深いのが、厚さわずか平均0.2mmの表皮です
表皮は外胚葉由来の細胞で、実は脳や神経系も同じく外胚葉から分化しています
つまり、脳は身体の最も外側にある表皮細胞を通して外界の情報を探っている、、
そんなふうにも考えられます
さらに近年の研究では、表皮細胞が受けた刺激が自律神経系の中枢である「視床下部」に伝わる可能性が示唆されています
視床下部の役割
視床下部は、自律神経の調整だけでなく、ホルモン分泌の司令塔としても機能しています
脳下垂体を介して成長ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンを分泌させ、全身の恒常性(ホメオスタシス)を維持しているのです
また、視床下部は大脳辺縁系(情動や意欲、記憶に関与する領域)の影響も強く受けやすいため、外部からのストレスに非常に敏感です
そのため視床下部のコントロールが乱れると、いわゆる自律神経失調症のような状態になり、原因不明の体調不良、慢性的なだるさや痛みといった不定愁訴へとつながってしまいます
視床下部の乱れがもたらす症状
視床下部の機能異常は、摂食障害などの病態とも関係しています
たとえば、寒がりや頻尿といった一見無関係に思える症状も、視床下部の調整不全によるものだと考えられています
鍼灸治療のアプローチ
では、鍼灸はどのようにして視床下部を刺激するのでしょうか
鍵となるのは、厚さわずか0.2mmの表皮を意識することです
鍼をただ刺すだけでは十分な効果は得られません
鍼灸師はツボや経絡を通じて、視床下部に関連する経穴を的確に見極め、繊細にアプローチします
その結果、原因が特定しにくい症状であっても改善が期待できるのです
このため、激しい運動を行うスポーツ選手よりも、むしろ不定愁訴を抱える方に経絡治療が適しているといえます
神経症のある方であっても、その効果を実感されるケースがあります
なぜ症状が改善するのかを明確に説明できないこともありますが、表皮細胞と視床下部との関係を生理学的にイメージすることで、鍼灸の働きを理解しやすくなる感じはします
まとめ
経絡鍼灸治療は、
「皮膚、特に表皮細胞を通じて視床下部に働きかけ、体全体のバランスを整える」
ことを目指す治療法とも言えると思います
不定愁訴や自律神経の乱れに悩む方にこそ、その効果を実感していただける可能性があるように思います

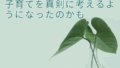

コメント