そういえば
あのお子さんが高校生だから、もう10年になりますでしょうか
吃音のお子さんの来院が続いていたことがありました
もちろん、必要に応じて病院の受診をおすすめしますが、
一過性の吃音であれば、自然と良くなることも少なくありません
ただ、「病院にも通っているのに、なかなかよくならない」と心配されて来院される方も多くいらっしゃいます
私の印象では、そういったお子さんに共通しているのが、、
とてもまじめで、がんばり屋さんだということ
発表会やお遊戯会、人前に立つ場面になると、つい完璧を求めて気負ってしまい、言葉に詰まってしまう
それをお友達に真似されて、ますます焦ってしまう、、
そんなループにハマってしまった子が多かったように思います
東洋医学的には、「脾と腎」あるいは「脾と肝」の関係が関わっていることが多く、
特に“実所見”をどう扱うかが治療のポイントになるかと思います
私の治療だと
「腎実(旺気)」を意識しつつ
脾の気を補うような治療を選ぶことが多いでしょうか?
吃音だけでなく、チックや貧乏ゆすり、髪をむしる、爪を噛む等々、
表に出しにくい不安やストレスが、体の動きとして現れている子どもたちは少なくありません
そんな子どもたちは、ほんとうに感受性が豊かで繊細で、そしてがんばり屋さん!!
だからこそ、家庭の中ではぜひ
「あなたはそのままで大丈夫」
――と伝えてあげてもらいたい
加藤諦三先生の本の中に、こんな言葉があります。
子どもに対する最大のプレゼントは、親の積極的な関心
ほんとうに、そのとおりだと思います。
積極的な関心といえば、
私は4人の子育ての中で「えこひいきしない」ことはかなり意識してきたつもりです
でも、正直これって正直とても難しい
なので、あえて一人ひとりにあえて「えこひいきする時間」をつくっていました。
たとえば月に一度は1対1で外出して、マクドナルドへ行ってみたり
そう、、
1対1の時間は子どもにとってとても貴重なんじゃないかな、って、、
実際兄弟4人ともなると、ナゲットをめぐってじゃんけん大会になったりするくらいなので(笑)、
えこひいきしないためにえこひいきする
自分が親から一番えこひいきされたと思えたら、えこひいきのことを微塵も思わないと思っていたので、結構意識していたように思います
兄弟それぞれ性格も思考もバラバラ
同じお腹から生まれてきても、本当にみんな違うんですよね
短所を挙げればきりがないけれど、
長所もまた、きりがない(笑)
だったら、長所をできるだけたくさん見つけて、褒めちぎってあげたい
そんなことも子育てには大切なことのように思います
最後に一つ
親の言うようには育たないけど、親のするようには育つ
ほんとうにその通りだと思います。
そして
「子どもを見れば親がわかる」
昨日も書きましたが、ちょっとドキッとする言葉ですよね??(笑)
子どもたちはすでに成人していますが
いまだに気をつけたいな、って思っちゃいます


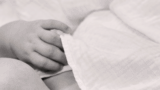
コメント