あいかわらず、DVや虐待に関するニュースが後を絶ちません
さきほどもラジオで、虐待を受けた子どもの話を聞きました
本当に胸が痛みます
そもそも「子どもを愛する」とは、どういうことを指すのでしょうか
私はずっと、子どもと一緒にいるだけで嬉しいし、それが当たり前の感覚だと思っていました
だからこうしたニュースを見るたびに、自分がどれほど恵まれていたかを思い知らされる感じです
そして、そんなふうに育ててくれた親に、あらためて感謝の気持ちが湧いてきます
独り身のときには、正直この気持ちがよくわかりませんでした
でも、自分に子どもが生まれて、ようやく親の思いが少しずつ理解できるようになった気がします
ただ、
子どもに対して、ちゃんと何かできていたかというと、
まったく自信はありません
できる範囲で精一杯やってきたつもりではありますが、
それをどう受け取ってくれているかは、子ども自身が判断すること
親の気持ちや行動が、どんなふうに子どもの中に残っていくのかは、
今の私にはわかりません
でも、いつか伝わると信じています
*
DVの話に触れて、ふと思ったことがあります
哺乳類というのは、生まれた直後から一定期間、年長者の手を借りなければ生きていけない存在です
これは、生まれる前からすでに“刷り込まれている本能”のようなものだと思うのです
動物の世界にも子殺しはありますが、多くの場合、年長者は本能的に
「自分より弱い存在を守り、育てる」ことを当然のことと思っています
そう考えると、乳幼児を暴力によって支配するという行為は、生物的な本能すら逸脱しているように思えるのです
特に人間は、動物の中でも極めて弱い個体です
だから人間は肩を寄せ合い、外敵と戦いながら子どもを育ててきました
ひとりで育てるのではなく、みんなで育てる
そこに、ないがしろにできない限界を越える力があったのではないでしょうか
*
江戸時代の子育てのあり方を見ると、
「帯親」「取り上げ親」「乳つけ親」「名付け親」「拾い親」「仮親」等、
実に多くの“大人”たちが、ひとりの子をよってたかって見守り育てていたことがわかります
つまり、子どもは社会で育てるものだったのです
だからこそ、何人産んでも今ほど親の負担は重くなかったのかもしれません
年配の方の中には
「昔はもっと大変だった」とおっしゃる方もいますが、
私はそうは思いません
今は人とのつながりが薄れ、近所の手も借りづらく、孤立しやすい時代
子育てに関しては、むしろ今のほうがずっと大変だと思うのです
*
おひとり様が当たり前のこの時代、
時折、「子どもなんて社会には必要とされていないんじゃないか」と感じることすらあります
でも、
それでも、
みんな、本当に頑張っていると思います
だからこそ、
子どもたちのことを、もう少し社会全体で見守れるような世の中になってほしい
そんなふうに、心から願っていますし、行動したいと思っています

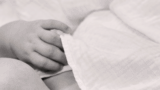
コメント