「お腹の赤ちゃんに愛情を持つことができません」
そんなふうに悩む妊婦さんは、少なくありません。
「お腹の中の赤ちゃんに愛情を持つ」
──この“愛情”という言葉、実はなかなかの曲者です。
私は「妊娠中に胎児への母性や愛情が自然と芽生えないのは当然のこと」だと考えています。
今日はその理由についてお話しします。
人は哺乳類です。
哺乳類は、触れ合うことで相手を探り、敵か味方かを判断する生き物。
つまり、触れるという行為こそが愛情のスタートラインなのです。
出産直後に母乳を吸わせることによって、母親はその子に愛情を注ぎ始めます。
実際、出産後すぐに母子を引き離すと、自分の子だと認識できなくなり、時に攻撃してしまうこともあるといわれています。
この「母子分離による影響」は、チンパンジーにも見られる現象です。
(参考:京都大学霊長類研究所 松沢哲郎教授の記事
親と離せば子育て不能に – 日本経済新聞)
この愛情の鍵を握るのが、「オキシトシン」というホルモンです。
母乳を与えることで多く分泌されるオキシトシンは、母親に「この子は自分の子だ」と感じさせ、実感としての愛情を育てていきます。
しかも、オキシトシンは授乳だけでなく、産後3日ほどの間に赤ちゃんを抱いたり、撫でたりすることでも分泌されるといわれています。
さらに興味深いのは、男性でも生まれたばかりの赤ちゃんに触れることで、このホルモンが分泌されるという点です。
私自身、オキシトシンについての本を読み、「生まれた赤ちゃんを“好きになる”のは、まさにこのホルモンの働きによるものなのでは」と思っています。
つまり、ホルモンレベルでの愛情は、妊娠中ではなく「出産後」に生まれるものと言えるでしょう。
最近では立ち会い出産も増え、父親が生まれたての赤ちゃんに触れる機会も多くなっています。
それが、子煩悩なお父さんが増えている理由のひとつかもしれません。
少し話が変わりますが、動物は本来、他者を怖れる存在です。
しかし、怖れだけでは「種族保存」も「個体維持」も果たせません。
だから、生まれてすぐのスキンシップがとても大切になります。
その触れ合いを通して愛情ホルモンであるオキシトシンが分泌され、
「敵か味方か」「怖れてよい相手か信頼する相手かどうか」を判断できるようになるのです。
つまり、妊娠中に胎児への愛情がまだ実感できなくても、まったく問題ありません。
生まれて、触れて、抱きしめて──そこから“本当の母性”が育まれていくのですから。


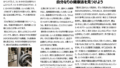

コメント